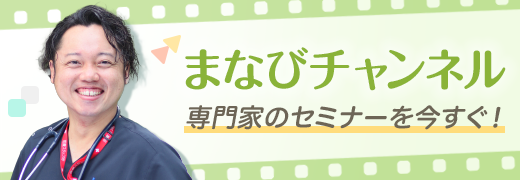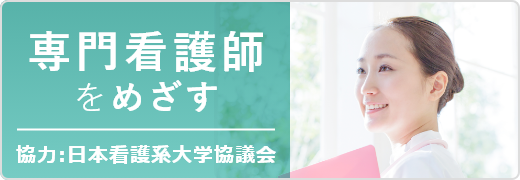肺炎に関するQ&A
【大好評】看護roo!オンラインセミナー
『看護のための病気のなぜ?ガイドブック』より転載。
今回は「肺炎」に関するQ&Aです。
山田幸宏
昭和伊南総合病院健診センター長
〈目次〉
- 1.肺炎ってどんな病気?
- 2.肺炎はどのように分類されるの?
- 3.細菌性肺炎はどんな症状が出現するの?
- 4.特発性間質性肺炎はどんな症状が出現するの?
- 5.肺炎の検査はどんなことを行うの?
- 6.細菌性肺炎の特徴的な検査所見は?
- 7.特発性間質性肺炎の特徴的な検査所見は?
- 8.肺炎の治療はどんなことを行うの?
- 9.肺炎の看護のポイントは?
肺炎ってどんな病気?
肺胞における炎症(memo1)が肺炎で、大部分は病原微生物による急性感染症です。ちなみに、上気道(鼻腔、咽頭、喉頭)に炎症が起こっている場合は上気道感染症、下気道(気管、気管支)に炎症が起こっている場合は下気道感染症です。炎症が胸膜に起こっている場合は胸膜炎といいます(図1)。
memo1炎症
病原微生物の侵入などによって細胞や組織が傷害されたときに、生体を守ろうとして起こる生体防御反応。炎症性サイトカインが産生される。発赤、熱感、腫脹、疼痛、機能障害が炎症反応のおもな症状である。

肺炎はどのように分類されるの?
肺炎には、いくつもの分類があります。
原因になる微生物による分類では、①細菌性肺炎、②ウイルス性肺炎、③異型肺炎(非定型肺炎、memo2)、④肺真菌症に分かれます。
細菌性肺炎は、細菌によって起こる肺炎です。細菌には肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、インフルエンザ菌、肺炎桿菌(かんきん)などがあります。ウイルス性肺炎は、インフルエンザウイルスなどのウイルスによって起こる肺炎です。異型肺炎は、マイコプラズマ、クラミジア、レジオネラなどによって起こる肺炎です。肺真菌症は、真菌によって起こる肺炎です。真菌には、アスペルギルス、クリプトコッカスなどがあります。
病理学的分類では、①大葉性肺炎と②小葉性肺炎に分かれます。大葉性肺炎は、病変が1つの肺葉全体に及ぶものです。小葉性肺炎は、病変が小葉単位に限られるもので、気管支肺炎とも呼ばれます(図2)。

(山田幸宏編著:看護のための病態ハンドブック。改訂版、p.45、医学芸術社、2007より改変)
炎症部位による分類では、①実質性肺炎と②間質性肺炎に分かれます。
実質性肺炎は、病変が肺胞の中にあるもので、肺胞性肺炎とも呼ばれます。原因は細菌です。
間質性肺炎は、病変が間質(肺胞と肺胞の間)にあるものです。原因はウイルス、マイコプラズマ、クラミジアなどの病原微生物、薬剤、放射線、アレルギーなどです。しかし、間質性肺炎の多くは原因不明の特発性のもので、特発性間質性肺炎と呼ばれます。
そのほか、誤嚥が原因となる誤嚥性肺炎(memo4)、長期臥床によって肺下部に血液がうっ帯し、それが原因となって感染を起こす沈下性肺炎などがあります。
memo2異型肺炎
マイコプラズマ肺炎は、発熱と激しい乾性咳嗽が出現し、小児や若年者に多く見られる。レジオネラ肺炎は、浴場や温泉などでレジオネラに汚染された煙霧質の吸引が原因になることがよくある。消化器症状や中枢神経症状を伴うことがある。
memo4誤嚥性肺炎
気道に食物や異物が入ってしまうことを誤嚥といい、その結果、生じる肺炎を誤嚥性肺炎と呼ぶ。口腔内の常在菌(おもに緑色レンサ球菌や嫌気性菌)により、気管支肺炎が生じる。喀痰の排出能や体力の低下した術後患者や意識レベルの低下した人、高齢者や小児(新生児)でとくに発生しやすい。
細菌性肺炎はどんな症状が出現するの?
細菌性肺炎のおもな症状は、発熱、痰、咳嗽、胸痛、呼吸困難です。風邪のような症状の後に、悪寒・戦慄を伴って高熱を発するケースがほとんどです。
痰は炎症によって気道粘液の分泌量が増加するために生じ、痰を排出しようとして湿性咳嗽が起こります。胸痛は、炎症が胸膜や横隔膜に及ぶと痛覚を刺激するために起こります。咳嗽に伴い胸痛が増強するため、痰の排出が困難になります。呼吸困難は、肺胞内に粘液が貯留してガス交換の面積が減少するために起こります。
また、主症状に伴い、全身倦怠感、食欲不振、関節痛、頭痛などが生じます。
特発性間質性肺炎はどんな症状が出現するの?
特発性間質性肺炎のおもな症状は、乾性咳嗽と呼吸困難です。間質性肺炎は、進行すると肺が線維化して硬くなり、膨らみにくくなります。その結果、空気を十分に取り込めず、呼吸困難が出現します。肺胞壁が肥厚するためにガス交換が障害されることも、呼吸困難の原因です。
肺炎の検査はどんなことを行うの?
肺野の聴診、胸部X線検査、CT検査、血液検査、動脈血ガス分析、喀痰検査などです。
血液検査には、ウイルスやマイコプラズマなどを検出する血清抗体価検査と、炎症反応を調べるC反応性タンパク質(CRP)、白血球数、赤血球沈降速度などがあります。喀痰検査は、原因となっている病原微生物を検出するために行われます。
細菌性肺炎の特徴的な検査所見は?
細菌性肺炎は、肺胞内に粘液が貯留しているために、病変部に肺性副雑音(ラ音)が聴取されます。胸部X線写真では、浸潤陰影が見られます(図3)。CT検査では、浸潤陰影の性状や広がりを知ることができます。血液検査では、CRP陽性、白血球数の増加、赤血球沈降速度の亢進など、炎症所見が認められます。動脈血ガス分析は、重症例では動脈血酸素分圧が低下し、動脈血二酸化炭素分圧が上昇します。

特発性間質性肺炎の特徴的な検査所見は?
肺野の聴診では、肺底部にパチパチとはじけるようなベルクロラ音(memo5)が聴取されます。胸部X線写真では、すりガラス状陰影と肺部の縮小が認められるのが特徴です。血液検査では、CRP陽性、白血球数の増加、赤血球沈下速度の亢進など、炎症所見が認められます。
肺炎の治療はどんなことを行うの?
病原微生物による肺炎の場合は、原因となっている病原微生物を同定し、その病原微生物に効果がある抗菌薬が処方されます。ところが、原因菌を同定するためには数日、効果のある抗菌薬を調べる薬剤感受性試験の結果が出るまでには数日から数十日もかかるため、原因菌を推定して抗菌薬が処方されます。これをエンピリック治療といいます。
特発性間質性肺炎には、副腎皮質ステロイド薬や免疫抑制薬などが使用されます。しかし、予後は不良です。
肺炎の看護のポイントは?
肺炎は全身性の消耗性疾患ですから、急性期は、心身を安静に保って酸素消費量とエネルギーの消費量を最小限に抑えることがポイントです。同時に、発熱や炎症症状に伴う苦痛を緩和します。
呼吸数や脈拍、チアノーゼの有無などを観察し、呼吸不全の発生を早期に発見することも重要です。
回復期は二次感染や合併症の予防に努め、退院前には感染予防のための生活指導を行いましょう。
⇒〔病気のなぜ?〕記事一覧を見る
本記事は株式会社サイオ出版の提供により掲載しています。
[出典] 『看護のための病気のなぜ?ガイドブック』 (監修)山田 幸宏/2016年2月刊行/ サイオ出版