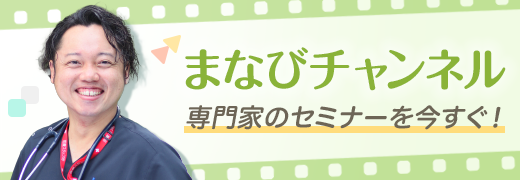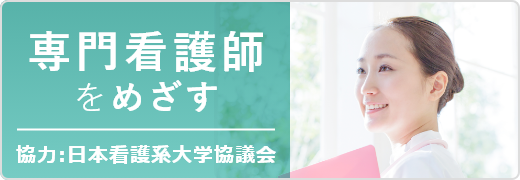皮膚悪性リンパ腫|悪性腫瘍⑨
『皮膚科エキスパートナーシング 改訂第2版』(南江堂)より転載。
今回は皮膚悪性リンパ腫について解説します。
瀧川雅浩
浜松医科大学名誉教授
Minimum Essentials
1リンパ球系細胞が悪性化し、皮膚で増殖する疾患である。菌状息肉症、セザリー(Sézary)症候群が代表的な疾患である。成人T細胞白血病/リンパ腫(ATL)では、約半数の患者に皮膚病変が出現する。
2紅斑、丘疹、結節、腫瘤などが単~多発する。時にかゆみを伴う。全身症状は進行すると出現する。
3病型分類、病期に基づき、治療法を選択する。菌状息肉症では病初期には紫外線療法、進行すると化学療法が選択される。
4経過は、菌状息肉症ではゆっくりであるが、セザリー症候群では比較的早い。ATLは病型による。治療により経過を遅らせることができるが、いずれも致死的である。
皮膚悪性リンパ腫とは
定義・概念
悪性化したリンパ球系細胞が皮膚で増殖する疾患で、代表的なものに菌状息肉症、セザリー症候群がある。
また、成人T細胞白血病/リンパ腫(ATL)では、ヒトT細胞性白血病ウイルス1型(HTLV-1)に感染したT細胞が悪性化し、全身臓器で増殖する。約半数の患者で腫瘍細胞の増殖による皮膚病変が生じる。
原因・病態
菌状息肉症、セザリー症候群では特定されたものはない。ATLではHTLV-1のT細胞への感染が密接に関連している。
日本皮膚科学会による全国調査では、毎年約400名の皮膚悪性リンパ腫患者が新規登録されている。約半数が菌状息肉症あるいはセザリー症候群であるが、菌状息肉症が90%以上を占める。両疾患とも致死的である。
菌状息肉症は数年から10数年かけてゆっくりと進行し、長い経過をとる。一方、セザリー症候群はまれな疾患であるが、末梢血に異型リンパ球が出現し、経過は比較的早い。
HTLV-1感染者(キャリア)は西南日本沿岸部を中心に110万人ほど存在し、感染者のATL発症率は年間1,000人に0.6~0.7人である。
感染から発症までの潜伏期間が長く、キャリアが生涯に発症する確率は約5%で、発症ピークは60歳ごろである。ATLの予後は病型によりさまざまである。
目次に戻る
診断へのアプローチ
臨床症状・臨床所見
菌状息肉症は以下の3病期でゆっくり進行する。
紅斑が目立つ湿疹として生じ(紅斑期)(図1)、時に強いかゆみを伴う。

徐々に湿疹部全体が盛り上がり、厚く触れる(浸潤する)ようになり(扁平浸潤期)、その上に丘疹、結節、腫瘤を形成する(腫瘤期)(図2)。
浸潤を触れる紅斑が全身に広がっている。結節(←)もみられる。

さらに進行すると、皮膚リンパ腫細胞がリンパ節、他臓器へ浸潤する。セザリー症候群は全身の皮膚が赤くなる紅皮症(図3)で発症し、進行すると丘疹、結節、腫瘤を形成する。

ATL の病型には、急性型、リンパ腫型、慢性型、くすぶり型がある。約半数の患者に紅斑、丘疹、結節、腫瘤、紅皮症など多彩な皮膚症状がみられ、菌状急肉症、セザリー症候群との鑑別を要する。
検査
皮膚の病理組織検査で異型リンパ球の浸潤を認める。確定診断には、免疫染色や遺伝子検査を併せて行う。同時に、血中の異常細胞の有無、リンパ節や他臓器の病変なども検索する。
セザリー症候群では病初期から末梢血中に異型リンパ球(セザリー細胞)が出現する。ATLは抗HTLV-1抗体陽性である。
目次に戻る
治療ならびに看護の役割
治療
おもな治療法
症状、病期に応じて以下の治療法を選択する。
(1)発疹に対する治療
ステロイド薬外用、紫外線療法(PUVA[プーバ]療法、ナローバンドUVB療法)、電子線照射が行われる。
(2)化学療法
ゾリンザ®内服、イムノマックス-γ®点滴静注、タルグレチン内服、ポテリジオ®点滴静注、CHOP療法など。
治療経過・期間の見通しと予後
治療により経過を遅らせることはできるが、いずれも致死的である。
看護における役割
治療における看護
致死的疾患ではあるが、早期にはとくに生活の制限はない。規則正しい生活を送り、ストレスをためないようにする。しかし、時に経過が長く、継続した治療が必要となるため、患者と家族へのさまざまな指導と精神的フォローが大切である。
外来で治療を行う場合、治療期間は一般的に長期間にわたることが多い。感染症に注意するよう指導する。感染予防には手洗いやうがいをこまめに行う、部屋を清潔にするなどの工夫が必要である。
放射線療法、化学療法が選択された場合、悪心・嘔吐、脱毛、骨髄抑制などの副作用出現による身体的・精神的苦痛が予想されるので、治療前のインフォームド・コンセントをしっかり行う。
また、副作用に対し適切な処置を行い、患者が安心して治療を受けられるように支援する。
(1)悪心・嘔吐
制吐薬の投与により、ある程度予防できる。心理的要因で誘発されることもあり、患者の心理状態を把握することが大切である。食事を患者の嗜好に合わせるよう配慮する。
(2)脱毛
治療が終了すれば必ず生えてくる。抜け毛に対してネットや帽子などの利用を勧める。
(3)骨髄抑制
白血球数が減少するので、感染症予防対策を行う。
・化学療法前に齲(う)歯、痔などがあれば、それに対する治療を行う。
・身体の清潔を保つ:手洗い、うがいの励行、皮膚の清潔など。
・病室の管理:個室管理、ガウンテクニック、面会人の制限、掃除の徹底、クリーンベッドの使用など。
・食事:生ものを避け加熱する、無菌食など。
フォローアップ
退院後しばらくは、疲れたら無理をしないですぐに横になるようにする。軽い運動や簡単な家事をしながら、体力の回復に努める。
目次に戻る
本連載は株式会社南江堂の提供により掲載しています。
[出典] 『皮膚科エキスパートナーシング 改訂第2版』 編集/瀧川雅浩ほか/2018年4月刊行/ 南江堂