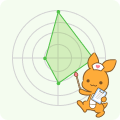【テンプレートあり】封筒・提出マナーも 看護師の退職願・退職届の書き方
退職時に必要になる退職願や退職届。
はじめて作成する看護師さんに向けて、書き方や封筒マナー、提出する相手やタイミングなど、退職願・退職届について気になるポイントをまとめました。
目次
【テンプレート】看護師の退職願・退職届
退職願のテンプレート

退職届のテンプレート

封筒の書き方

退職願・退職届や封筒で使用する筆記用具は、黒色の油性インクのボールペンや万年筆がオススメ。
サインペンや筆ペンでもOKですが、文字がにじんで読みづらくならないように注意しましょう。
退職願・退職届の書き方ポイント5つ
退職願・退職届を書くときのポイントは5つ。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
退職願・退職届の書き方5つのポイント
退職願は退職交渉のとき/退職届は退職交渉が済んだ後

退職願と退職届の違いは、提出のタイミングです。
- 退職願
「これから退職交渉を行う」という場合は退職願を提出します。上司に手渡した後も、院長や理事長などが承諾するまでは撤回することができます。
※ただし、退職願は交渉が難航しているときに形に残る意思表示として提出する場合が多く、不要なことがほとんどです。
- 退職届
「退職交渉が済んでいる」という場合には退職届を提出するのが一般的です。退職届は、よほどの事情がない限りは撤回することができません。
どちらも、いきなり提出するのはNG。まずは師長など直属の上司に退職の相談をしてから提出するようにしましょう。
キャリアアドバイザー
病院や施設によっては、退職願や退職届を書いて提出するのではなく、決まった形式の書類に署名・捺印をするケースも。
勤め先のルールを確認しておくと、手続きがスムーズです。
便箋はB5の白無地、封筒は白の長形4号

- 便箋:B5/A4の白無地の縦書き
便箋は白無地の縦書きのものを使用します。サイズはB5が一般的ですが、A4でも問題ありません。
色・柄付のものや、和紙などの凹凸のあるものは退職の書類には適しませんので、注意してください。
- 封筒:白の和封筒(長形4号/3号)
封筒は白色の和封筒を使用します。サイズは退職願・退職届がB5なら長型4号(90×205mm)、A4なら長型3号(120×235mm)です。
茶色の封筒は、事務的な書類を送る際に使用するもので、正式な書類には適しません。
- 便箋の折り方:三つ折り

便箋は三つ折りが基本です。図を参考に三つ折りにし、封入しましょう。
退職願・退職届は手書きが基本
退職願・退職届は、手書きが基本です。手書きの方がより誠意を示すことができるためです。
とはいえPC作成でもOKな職場も増えているので、気になる場合は上司や辞めた同僚などに確認してみましょう。
なお、PC作成でも自分の名前は印刷後に手書きし、捺印します。
職場によっては就業規則に書き方の指定がされていることもあるので、あわせて確認しておきましょう。
退職理由は「一身上の都合」でOK
退職理由は「一身上の都合」と書きましょう。
たとえ本当の理由が「転職をする」「引っ越しをする」「人間関係が良くない」といった場合でも、自分から退職を願い出る場合はすべて「一身上の都合」が理由となります。
誰に出す?提出は師長、宛名は院長!

退職に関する書類を提出するのは直属の上司である師長ですが、実際に退職願や退職届に書く宛名は施設の院長(または理事長)です。
誤って宛名を師長にしないように注意しましょう。
ただし、クリニックなどの小規模な施設の場合は、宛名同様に院長に提出することもありますので、あらかじめ確認をしましょう。
退職願・退職届はいつ提出する?
退職を決意してからの時系列で、退職願・退職届を提出するタイミングを見ていきましょう。
退職の決意をしたら、
まずは直属の上司に相談をする
退職の相談に日数がかかる
or
対応をしてもらえない場合は
直属の上司に「退職願」を提出する
※スムーズに退職交渉が進んだ場合、
退職願は不要なこともあります。
退職交渉の末に退職が承認されたら、
上司と相談の上、正式な退職日を決める
就業規則や上司の指示に沿って
正式な退職日を記載した
「退職届」を提出する
いきなり退職届・退職願を突きつけることは失礼になってしまうので、まずは相談から始めましょう。
退職願・退職届は手渡し?郵送?
退職願・退職届は手渡しが基本
退職願や退職届は、通常通り勤務していれば、直属の上司に手渡しするのが基本です。
しかし例外として、病気や怪我などで勤務先に行けない場合や、休職しているなどの理由があるときは、一度直属の上司に電話などで相談し、指示に従いましょう。
場合によっては退職願・退職届を郵送するよう、指示されることもあるでしょう。
郵送するときは、封筒を二重にする

退職願・退職届を郵送するときに注意したいのは、「退職願・退職届」と書いた封筒に直接宛先の住所を書かないこと。
封をしたら、別の一周り大きめのサイズの封筒に入れて、郵送をしましょう。
退職願・退職届を入れた封筒が長型4号なら長型3号(定形郵便物)、長型3号なら角5号(定形外郵便物)がベストな大きさです。
強い引き止めを受けていて退職願・退職届を受け取ってもらえないときや、どうしても上司と連絡が取れないときは、最終手段として退職届を内容証明郵便(※)で郵送することで、退職すること自体は可能です。
その場合、退職届が病院に到着した日の2週間後に法的に退職が成立します。
ただし、これは一方的に退職意思を突き付ける形になってしまうため、よほどの事情がない限りは、手渡しをすることが基本です。
そのほか、よくある退職時のトラブルとその対処法については、下記の記事で解説しています。
※内容証明郵便とは…提出したことを公的に証明できる郵送方法。紛失などで相手に届かないといったリスクを回避することができます。
内容証明郵便の出し方はこちら:内容証明|日本郵便
退職届が完成したら…
退職届を提出できたら、引き継ぎや有給消化をしたのちに退職となります。
下記の記事から、退職日までの流れややるべきこと、注意点などを確認しておきましょう。
また、下記の記事では、退職日までに必要な手続きや返却するもの・受け取る書類などをまとめています。こちらもぜひ参考にしてみてください。